用語解説
glossary- 圧密沈下(あつみつちんか)
-
土に外部から圧力が加わると、土は圧縮され、ひずみが生じる。土は土粒子と水と空気で構成されて、飽和状態にある透水性の低い粘土は、外部からの圧力を受けても直ぐに圧縮せずに、長時間かけて圧縮する。これを圧密といい、圧密により地盤が沈下することを圧密沈下といいます。
- 埋立地(うめたてち)
-
埋め立てられた土地
- 液状化(えきじょうか)
-
地下水位が高く緩い砂地盤では、地震が発生すると粒子間の水圧が急上昇して強度を失い、液状のようになる現象を『液状化』といいます。
- N値(えぬち)
-
ボーリング調査に伴う標準貫入試験により測定される、地盤の強度を表す指標のひとつ。ロッド(鉄管)の先端にサンプラー(土の採取用部品)を付け、重さ63.5kgのハンマーを76cmの高さから落下させ、サンプラーが30cm貫入するのに必要な打撃回数のこと。基本的には、数値が大きいほど硬く締まった地盤と判断できます。
- オートマチックラムサウンディング(おーとまちっくらむさうんでぃんぐ)
-
オートマチックラムサウンディングは、スウェーデンで開発され、1974年に日本に導入された試験方法。試験は、専用ロッドの先に先端角90度、外径45mmのコーンを取り付け、自動連続貫入装置で貫入していき、貫入量20cmごとの打撃回数を測定。さらに、決められた貫入量ごとにトルクを測定し、打撃回数の補正を行ってNd値とする。補正後のNd値は標準貫入試験のN値とほぼ同じであるといわれています。

試験機
- 瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)(かしたんぽりこうほう)
-
新築住宅の供給を行う建設業者又は宅地建物取引業者が一般の消費者と請負契約又は売買契約を締結した場合、消費者保護の観点から建設業者又は宅地建物取引業者は資力確保措置を講ずる必要がある事等を定めた法律。尚、宅地建物取引業者との契約は対象外となっている。また、資力確保措置の義務対象となる瑕疵担保責任の範囲は、<住宅品質確保法上の特定瑕疵担保責任の範囲と同様で、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入防止部分をいいます。
- 干拓地(かんたくち)
-
湖や海の水深の浅い部分を提防で囲み、農地を作る目的で排水して陸地化した土地。
- 崖錐(がいすい)
-
山地、丘陵の急斜面から落下した岩屑が崖下に堆積して形成された地形。
- 基礎設計(きそせっけい)
-
建設省告示第1347号により、布基礎、べた基礎の最低の仕様があるが、基礎の設計においては、瑕疵担保履行法に基づく保険法人の設計施工基準を考慮した計画や、物件毎に構造計算を行った計画の実施が必要となる場合があります。
- 旧河道(きゅうかどう)
-
蛇行が激しく水害がたびたび起こる暴れ川などで、河川を直線に改修したあとなどに残る、元の川の流れのあと。
- 丘陵(きゅうりょう)
-
一般的に平地と山地との中間的ななだらかな地形をいいます。
- 許容応力度(きょようおうりょくど)
-
地盤に荷重を加えた時、大きな変形を起こさず安全と考えられる最大限の荷重。
- 切土(きりど)
-
元々斜面になっている土地の地面を切り崩し、家を建てられるような平坦な土地を作ること。
- 空中写真(航空写真)(くうちゅうしゃしん)
-
空中から撮影した写真。地形図よりも詳細な微地形判読とその他の情報を迅速かつ広範囲に入手できます。判読する情報は、地形の傾斜、斜面形、斜面交換線・起伏量と谷密度、災害地形の種類とその分布などの地形要素と色調・きめ・模様などの写真画像の要素になります。広域にわたって迅速に情報が入手できる特徴から、植生に関する情報や各種災害関連情報の収集には欠かせない手法となっています。
- 黒ぼく(くろぼく)
-
腐植に富み、軽くて粘りけの乏しい黒色の土壌。
- 傾斜角(けいしゃかく)
-
水平面からの傾きの角度
- 間知石(けんちいし)
-
石材に一定の加工をした規格石材。石垣や土留に用いる土木建築材料。
- 現地踏査(げんちとうさ)
-
周辺家屋、道路などの異常の状況から地盤沈下の危険性を調べる。切土、盛土などの造成形態から不同沈下の危険性を調べる。工事の施工性、障害物等を把握します。
- 洪積層(こうせきそう)
-
洪積層は沖積層より標高の高い台地・段丘・丘陵地などに見られる地層。
- 後背湿地(こうはいしっち)
-
河川沿いに発達する自然堤防背後の低平地(自然堤防より1m前後低い)を後背湿地という。堆積物は粘土やシルトなどの細粒物質が多く、局所的には有機質土をはさむこともあります。
- 谷底低地(こくていていち)
-
山地・丘陵地の谷部や台地上の谷部に刻まれた谷部に堆積した沖積地盤で軟弱地盤が多い。また、斜面に接する谷の両端部は元の地形が傾斜してしていることから、不同沈下の原因となることがあります。
- 砂州(さす)
-
沿岸海流や波の作用で運ばれてきた砂が堆積し海面上に現れたもの。
- 山地(さんち)
-
比較的大きな起伏や傾斜を持ちまわりより高い地域で、複数の山からなる広い地域を指します。
- 支持力(しじりょく)
-
地盤が支えることのできる力の大きさ。
- 指定調査機関(土壌汚染調査)(していちょうさきかん)
-
土壌汚染調査〔フェーズⅠは除く〕は、環境大臣が指定する調査機関(指定調査機関)が行わなければならない。
- 植生(しょくせい)
-
ある地域に生育する植物の集まり。植生は表層土の硬軟や水分の含み具合により左右される。したがって、どのような植生が生えているかによって地盤状況を推定する事が出来る。地形的要因だけでなく、地形に伴う地表含水状況の違いや表層の厚さが関係している。一般的な根の深さは、地上から木の高さの1/5~17に達すると言われており、これを目安に伐根により地表面の乱されている深さを想定することもできます。
- 資料調査(しりょうちょうさ)
-
関連する過去データや文献から情報を収集する事。
- 地業(じぎょう)
-
基礎構造のうち地盤に対して行う工事。割栗地業、杭地業などのこと。
- 自沈層(じちんそう)
-
スウェーデン式サウンディング試験等の試験で、おもりの重さだけで先端部が地面に沈む層。
- 地盤の耐力(地耐力)(じばんのたいりょく(ちたいりょく))
-
地盤が建物を支える力(耐力)、地盤の強さ、地盤収縮、地盤の変形の3項目を検討解析した評価。
- 地山(じやま)
-
人工的な地盤(盛土・表土など)に対し、それらの下に隠されている自然のままの(元々の)地盤のこと。
- スウェーデン式サウンディング試験(すうぇーでんしきさうんでぃんぐしけん)
-
"1917年にスウェーデン国有鉄道が初めて使用し、フィンランド、ノルウェーなどの諸国で広く実施された試験法。1976年にJIS A 1221「スウェーデン式サウンディング試験方法」として、JIS規格に制定された。今日では、戸建住宅など小規模建築物を建設する際、地盤の支持力性能を評価するのに広く用いられている。
スウェーデン式サウンディング試験は、地表面から深度10mまでの土の硬軟、締まり具合などを判別するための抵抗値を求める試験であり、戸建住宅など小規模建築物を建設する際の地盤調査に広く使われています。
作業・記録全てを手で行う手動式、作業のみ機械で行う半自動式、全て機械で行う自動式などがあります。"
- 潟湖跡(せきこあと)
-
砂州や砂丘の背後側の湿地帯で葦などの湿地性植物などが生え、軟弱地盤となっています。
- 設計地耐力(せっけいちたいりょく)
-
設計時に設定した基礎底面から地盤へかかる力(荷重)のことで、建物荷重、基礎の底面積、基礎の形状により設定されます。
- 扇状地(せんじょうち)
-
山地部の谷の出口から平野部へ向かって扇状に広がる緩傾斜の半円錐状の地形扇状地といいます。一般に不規則な粒径分布の砂礫からなり、地下水は扇頂付近では低く、扇端部では高い。砂礫を主体とし概ね安定した地盤になります。
- 段丘(台地)(だんきゅう(だいち))
-
海岸段丘は海進と海退の繰り返しで海岸平野に数段の段丘が形成されたもので、河岸段丘は河川勾配の変化と流路の移動によって形成されたもので、比較的安定した地盤になります。
- 置換工法(ちかんこうほう)
-
表層の軟弱層などを良質土に置き換え、良好な地盤とする工法。
- 地形区分(分類)(ちけいくぶん(ぶんるい))
-
地表面を類似の地形が占める広がりにより、区分・分類し、地形区分を設定すること。
- 地形図(ちけいず)
-
地形図には等高線、土地利用状況などが示されており、地盤が良いか悪いかなどの参考となる。地表面の傾斜は、等高線の密度で読み取ることができ、等高線の密度の高いところは傾斜が急で、密度が低いところは傾斜が緩やかであることを示している。
- 地耐力(ちたいりょく)
-
直接基礎を計画するためには、地耐力が問題となる。地耐力とは、支持力と沈下の両方を検討したものである。支持力(破壊)と沈下(変形)が、混同されていることが多いが、小規模建築物では重量が軽いので支持力破壊を起すことはほとんどない。
- 沖積層(ちゅうせきそう)
-
約2万年前の最終氷期最盛期以降に堆積した地層。標高の低い低地に多く見られる。主に流水によって運ばれてきた土砂などが積み重なって堆積した地層です。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(ちょうきゆうりょうじゅうたくのふきゅうのそくしんにかんするほうりつ)
-
長期優良住宅に認定された場合、税の特例措置及び住宅ローンの供給の支援を受けることが出来きます。
- 提間湿地(ていかんしっち)
-
浜提と浜提の間の湿地帯を提間湿地又は提間低地という。含水量の多い粘土、シルト、有機質土からなっています。
- 電気式静的コーン貫入試験(三成分コーン貫入試験)(でんきしきせいてきこーんかんにゅうしけん)
-
三成分コーン貫入試験は、コーンを貫入することにより先端抵抗、間隙水圧、周面摩擦抵抗を求め、地盤の土質を始め強度などを推定するもの。
- 特定有害物質(とくていゆうがいぶしつ)
-
第1・2・3種特定有害物質に区分されており、それぞれ、第1種特定有害物質とは揮発性有機化合物11物質、第2種特定有害物質とは重金属類10物質、第3種特定有害物質とは、農薬類とPCB5物質と定められています。
- 土壌汚染対策法(どじょうおせんたいさくほう)
-
土壌汚染対策法は2002年5月に制定され、2003年2月15日に施行された法律。特定有害物質を扱っていたことのある工場等が対象となっており、土壌汚染対策法以外にも各都道府県での環境条例等により土地の改変時等の調査義務が発生する場合があります。
- 土壌汚染調査フェーズII(どじょうおせんちょうさふぇーず2)
-
表層土壌のサンプリング(間隙ガス含む)を行い、含有化学物質等を公定法分析による分析を行い土壌汚染の可能性を判断する調査。
- 土壌汚染調査フェーズIII(どじょうおせんちょうさふぇーず3)
-
フェーズIIで得られた結果をもとに、深度方向への汚染の拡散状況を把握する為の詳細調査。
- 土壌汚染調査フェーズI(どじょうおせんちょうさふぇーず1)
-
土地の利用履歴等の地歴調査を中心とする資料等による机上調査。
- 土壌含有量(どじょうがんゆうりょう)
-
土壌に関する直接摂取によるリスクに係わる基準。土壌に含まれる化学物質の濃度の基準。
- 土壌溶出基準(どじょうようしゅつきじゅん)
-
地下水等の摂取によるリスクに関する基準。土壌から地下水等に溶け出す濃度基準。
- ネガティブフリクション(ねがてぃぶふりくしょん)
-
負の摩擦力 の事で、厚く堆積した軟弱地盤や盛土の地盤に沈下が生じると 杭を引き下げる力が作用します。 この負 の摩擦力は相当に大きく、杭先端の地盤を破壊して建物を沈下させる場合があります。
- 粘性土(ねんせいど)
-
粘り気が強い。水を通しにくい。拘束圧に関係なく強度が一定。含水比が高く、強さや硬さが含水比によって大きく変化する。間隙が大きく、変形しやすい。
- 標準貫入試験(ひょうじゅんかんにゅうしけん)
-
ボーリングにより孔(穴)を掘るのと並行して、一般に深度1.0mごとに実施する試験方法。ロッド(鉄管)の先にサンプラー(土の採取器)を付け、63.5kgのハンマー(おもり)を76cmの高さから自由落下させ、サンプラーが30cm貫入するのに要した打撃回数(N値)を測定することで、土の貫入抵抗を求めることができる。また、それと同時に地層の土のサンプルを採取することができます。
- 表面波探査(ひょうめんはたんさ)
-
起震機により、地震波の一種である「表面波」を人工的に地盤に流し、センサーによって検出することで、表面波が地盤を通過する伝播速度で地盤の性状を調査します。

表面波探査試験機 
試験機モニター
- 品確法(正式名称:住宅の品質確保の促進等に関する法律)(ひんかくほう)
-
"平成12年4月1日に、(1)住宅の品質確保の促進、(2)住宅購入者等の利益の保護、(3)住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決、を目的として施行された法律。
新築住宅の取得契約(請負/売買 平成12年4月1日以降の契約)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づけられました。"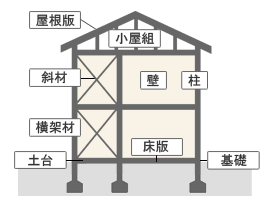
10年瑕疵担保責任の対象となる部分
- 不同沈下(不等沈下)(ふどうちんか)
-
地盤が建物自体の重さを支えることができずに不均等に沈下していく現象のこと。埋立地や軟弱地盤で発生しやすいといわれており、建物が傾くことで、外壁・内壁に亀裂が走ったり、ドアや窓の開閉が困難になったりすることがあります。
- プレキャストコンクリート(ぷれきゃすこんくりーと)
-
工場などであらかじめ製造されたコンクリート製品、プレキャストと略して呼ぶこともあります。
- 平板載荷試験(へいばんさいかしけん)
-
基礎底面となる地盤表面において直径30cmの載荷板を垂直方向に加力し、荷重 - 沈下量の関係より地盤の極限支持力(qd)を求めます。
- 変形角(へんけいかく)
-
水平面からの傾きに関わらず部分的に傾く角度
- 盛土(もりど)
-
元々斜面になっている土地に新たに土を盛り、家を建てられるような平坦な土地を作ること。また、元々平坦な土地でも、土を盛って地面を高くする場合もいう。
- 擁壁(ようへき)
-
高低差のある土地で、側面の土が崩れるのを防ぐために設置される壁状の構造物
